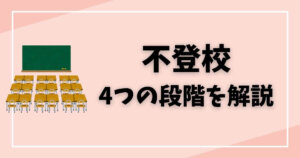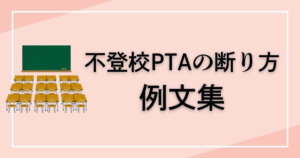不登校や体調不良など、さまざまな事情で学校に通えないお子さんを持つ保護者の方にとって、「オンライン 授業 出席 扱い 文部 科学 省」の制度がどうなっているのか気になる方も多いのではないでしょうか。最近では、文部科学省がオンライン授業を出席扱いとする制度を整備し、自宅学習やリモート授業でも出席日数として認められるケースが増えています。
本記事では、オンライン授業やリモート学習を活用しながら、文部科学省の制度を理解し、出席扱いを目指すためのポイントを詳しく解説します。内申点や進路にも大きく関わる重要な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むとわかること👇
・オンライン授業が文部科学省の出席扱い対象になる条件 ・出席扱い制度の具体的な仕組みと運用方法 ・フリースクールやホームスクールの出席扱い可否 ・内申点や進路への影響を抑えるための活用法

オンライン授業は文部科学省の出席扱い対象
出席扱いとはどういう意味?
出席扱いとは、本来なら学校に登校していない日でも、一定の条件を満たしていれば「出席したもの」として記録される制度のことです。一般的に、小中学校や高校では、生徒が学校に登校した日数が「出席日数」として記録され、成績や内申書に影響を与えます。しかし、不登校や病気、特別な事情がある場合には、この出席日数が大きな負担になることも少なくありません。
そこで注目されているのが、この「出席扱い」制度です。例えば、自宅での学習やオンライン授業など、学校外で学習活動を行った場合でも、学校の判断で出席日数として認められることがあります。つまり、物理的に教室にいなくても学習の成果や状況をきちんと確認できれば、「その日は学校に行った」とみなされるわけです。
これには大きなメリットがあります。特に不登校の児童生徒にとっては、家での学習が続けられるだけでなく、将来の進学に関わる内申点にも影響しない形で学校生活を継続できます。これまで「休んでいたから仕方がない」と思われがちだった日々の学びが、しっかり評価対象になる仕組みといえるでしょう。
ただし、この制度を活用するためには、学習の内容や成果を学校が把握できることが前提となります。そのため、保護者や学校、場合によっては学習支援機関などとしっかり連携し、適切な記録や報告を行うことが大切です。こうした取り組みによって、子どもの学びの機会を途切れさせずに支援することが可能になります。
文部科学省の出席扱いの要件は?
文部科学省が定める出席扱いの要件は、簡単に言えば「学校がその学習活動を出席として認めるかどうか」がポイントです。ただし、何でも出席扱いにできるわけではなく、いくつかの明確な条件が示されています。
まず、保護者と学校の連携がしっかり取れていることが大前提です。学習の進捗や内容を共有し、学校が学習の状況を正確に把握できる環境が必要となります。次に、学習活動そのものがIT機器などを活用しながら、計画的に実施されていることも条件の一つです。単なる自主学習ではなく、教師の指導や教材の提示があり、学びの成果を評価できる形になっている必要があります。
さらに、対面による指導の機会が設けられていることも大切なポイントです。たとえば、月に一度の登校や、オンラインでも直接やり取りする機会が求められることもあります。これは、子どもが孤立せず、学習の理解度をしっかり確認するためです。
これらの条件を満たしたうえで、最終的には校長が「出席扱いにしても問題ない」と判断することで、正式に出席扱いが認められます。つまり、親の判断だけでなく、学校側の理解と協力が不可欠なのです。
そのため、もし自宅学習やオンライン学習を出席扱いにしたい場合は、まずは学校に相談し、具体的な手順や必要書類について確認することをおすすめします。制度の運用は学校や自治体、教育委員会によって異なる場合もありますので、事前にしっかり話し合いをしておくことが重要です。
リモート授業は欠席扱いになる?
リモート授業が欠席扱いになるかどうかは、実はケースバイケースです。多くの保護者が気になるポイントですが、状況によって学校側の判断が分かれるため、しっかり理解しておくことが必要です。
まず、文部科学省の指針では、リモート授業が「正式な授業」として認められる場合、欠席扱いにはならず、出席扱いとして記録される可能性があります。ただし、この「正式な授業」とは単に自宅で動画を見るだけの学習ではなく、学校側が指導計画に基づき、教師による指導や成果確認がしっかり行われるものを指します。
例えば、ZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールを使って双方向の授業を受けたり、課題を提出しフィードバックを受けたりする形なら、出席扱いとなるケースが増えています。一方で、ただ動画を視聴したり、プリント学習だけで終わってしまう場合には、欠席扱いとされることもあるため注意が必要です。
また、学校によっては「リモート授業でも月に数回は登校すること」などの条件を設けている場合もあります。このように、リモート授業が必ずしも出席扱いになるとは限らず、あくまで学校や自治体の判断次第という面があるのです。
したがって、お子さんがリモート授業を受けている場合は、学校に「この授業は出席扱いになりますか?」と確認することをおすすめします。特に、内申点や進学に関わる大切な記録ですので、進学を考えている場合には学校との連携を密にして、安心して学びを進められる環境を整えていきましょう。
フリースクールの出席扱いの割合は?
フリースクールに通う場合、その活動がどの程度「出席扱い」になるのかは、多くの保護者が気になる点ではないでしょうか。実際、フリースクールは不登校の子どもたちの学びの場として広がっていますが、その出席扱いの割合は地域や学校によって差があるのが現状です。
文部科学省の調査によれば、全国的に見ると約6割程度の不登校児童生徒が、フリースクールなどでの学習活動を「出席扱い」として認められているという結果が出ています。これは思ったより高い数字かもしれません。つまり、多くの学校がフリースクールでの学習を、正式な学校教育の一部として評価し始めていると言えるでしょう。
ただし、ここで気をつけなければならないのは、出席扱いの基準が学校ごとに異なるという点です。たとえば、フリースクール側から提出される学習報告書の内容や、子どもの学習状況、通う頻度などが出席扱いの可否を左右することもあります。学校側が「しっかり学習している」と判断できる情報が不足している場合は、出席として認められないこともあるのです。
このため、フリースクールへの通学を出席扱いにしたい場合は、事前に学校としっかり相談することが大切になります。特に学期ごと、あるいは年度ごとに必要書類を提出するケースもあるため、フリースクール側とも連携を取りましょう。こうすることで、子どもの頑張りがしっかりと評価され、安心して学びを続ける環境が整えられるはずです。
高校生の不登校は出席扱いになりますか?
高校生が不登校になった場合、その間の学習が出席扱いになるのかどうかは、保護者にとって非常に重要な問題です。実は、この点については小中学校とは少し状況が異なります。現在のところ、文部科学省の制度では、高校生は自宅学習による「出席扱い」の対象にはなっていません。つまり、高校生の自宅学習は原則として出席扱いにはならないのです。
これは、高校教育が義務教育ではないため、学習評価や出席管理の仕組みが小中学校と異なることが背景にあります。もちろん、オンライン授業など学校が独自に取り組んでいる場合は別ですが、「不登校だから自宅で勉強すれば出席扱いになる」という仕組みは、高校生には適用されません。
ただし、一部の通信制高校やサポート校では、不登校の生徒でも学習した内容が評価され、単位取得につながる仕組みが整えられています。特に近年では、オンライン授業を導入する高校も増えており、登校しなくても学習が進められる環境が少しずつ整いつつあるのも事実です。
とはいえ、全ての高校でこうした対応が行われているわけではありません。もしお子さんが高校生で不登校になった場合は、学校の先生や学年主任に直接相談し、どのような制度や対応があるのかを確認することをおすすめします。場合によっては、通信制への転校や編入も一つの選択肢になるかもしれません。
ホームスクールの出席扱いはできますか?
ホームスクール、つまり家庭での学習を「出席扱い」にできるのか、気になる保護者は多いでしょう。結論から言えば、小中学校においては条件付きでホームスクールも出席扱いにすることが可能です。これは文部科学省が示すガイドラインに沿った対応で、学校としっかり連携することで実現します。
文部科学省は、不登校の児童生徒が自宅でICTを活用した学習を行う場合、一定の条件を満たせば出席扱いとすることを認めています。 具体的な教材名を公式に指定しているわけではありませんが、すららやベネッセなどが当てはまります。
このため、まずは保護者が学校と話し合いを行い、どのような形で家庭学習を進めるのかを明確にする必要があります。
一方で、高校の場合は先述の通り、ホームスクールでの学習は原則出席扱いにはなりません。したがって、この制度を利用できるのは主に小中学生に限られる点には注意が必要です。
いずれにしても、ホームスクールを検討する場合は、早めに学校側と相談し、具体的な計画を立てることが大切です。きちんとした手続きを踏むことで、お子さんの努力が「出席」として評価され、安心して家庭学習を進めることができるでしょう。
文部科学省の制度でオンライン授業が出席扱い
オンラインフリースクールは出席扱いになる?
オンラインフリースクールに通う場合、その学習が「出席扱い」になるのかは保護者の方にとって非常に気になるポイントでしょう。結論から言えば、オンラインフリースクールの利用でも、学校としっかり連携を取ることで出席扱いとなる可能性があります。
この背景には、文部科学省が示している「自宅など学校外の学習活動を出席扱いとする基準」があります。具体的には、学習計画がきちんと立てられ、教師や指導者によるサポートがあり、学習の成果がしっかり確認できる場合に出席として認められる仕組みです。オンラインフリースクールの多くは、この条件に合わせたカリキュラムや指導体制を整えています。
例えば、週に数回のライブ授業や、双方向のやり取りが可能なシステムを取り入れているスクールも多く、子どもが実際に学んでいる様子を学校側が把握しやすい工夫がされています。このような環境であれば、学校側も「出席扱い」として認めやすくなるでしょう。
ただし、すべてのオンラインフリースクールが出席扱いになるわけではないため、利用する前には必ず学校に相談しましょう。フリースクール側からの学習報告書や出席記録の提出が必要な場合もあるからです。さらに、自治体によって判断基準が異なるケースもあるため、事前確認は欠かせません。
オンラインフリースクールは、正しい手順と連携を踏めば出席扱いとして認められる可能性が十分あります。
オンラインフリースクールのデメリットは?
オンラインフリースクールは自宅で学べる便利な学習スタイルですが、いくつか注意すべきデメリットもあります。多くのご家庭が「自宅で無理なく学習できるなら」と考えるものの、思わぬ落とし穴があるのです。
まず大きな課題は「孤立感」です。自宅からオンラインで授業を受けられる反面、直接的な友人関係や人間関係を築く機会が限られてしまいます。特に思春期の子どもにとっては、人との関わりが少なくなることで、社会性を育む場面が減る可能性があるのです。
さらに、自己管理の難しさもデメリットの一つです。学校とは異なり、オンラインでは教師が常に隣にいるわけではありません。したがって、学習のペースを自分で管理する力が求められます。これは大人でも難しいことであり、子どもにとっては大きな負担になる場合も考えられます。
加えて、オンライン環境に依存することのリスクもあります。インターネット環境が整っていなければ授業に参加できず、通信トラブルや機器の不具合が原因で学習機会を失うこともあるでしょう。このような技術面の不安定さは、保護者としても気を付けたいポイントです。
こうしたデメリットを踏まえると、オンラインフリースクールを利用する際には、子どもの性格や生活環境をよく考えたうえで選択することが重要になります。特に、スクール側のサポート体制や、定期的な対面交流の機会があるかどうかなどを事前に確認しておくと安心です。
適応指導教室は出席扱いになるのですか?
不登校の出席扱いのメリットは?
不登校の子どもが出席扱いになる制度を活用することには、さまざまなメリットがあります。特に保護者にとっては、「学校に行けない間の学びが無駄にならないのか」という不安を軽減できる大きな支えになるでしょう。
まず、最も大きなメリットは「学びの継続が評価される」点です。子どもが学校に通えなくても、家庭やフリースクール、オンライン学習などで取り組んだ学習内容が、学校での出席日数に反映されます。これにより、将来の進路選択に必要な内申点や成績への悪影響を最小限に抑えることができます。特に中学生の場合は、高校入試での内申点が重要になるため、この制度が大きな助けとなるでしょう。
また、出席扱いになることで「欠席が続いている」という心理的な負担を和らげる効果も期待できます。長期間学校を休むと、どうしても子ども本人も「周りと差が開いてしまうのでは」「取り返せるのだろうか」と不安を感じることがあります。しかし、出席扱いによって学びの記録がしっかり残ることで、こうした不安を少しでも減らすことができるのです。
さらに、制度を活用することで、子どもが無理に登校する必要がなくなる場合もあります。例えば、精神的な負担や身体的な不調で登校が難しいときでも、自分のペースで学べる環境を確保しつつ、学習の評価を受けられるのです。これは親子にとって、非常に大きな安心材料になります。
もちろん、制度を活用するためには、学校との連携や学習記録の提出など、やるべきことも出てきます。しかし、その一手間をかける価値は十分にあると言えるでしょう。
出席扱い制度を利用すると内申点はどうなりますか?
出席扱い制度を利用した場合、内申点への影響がどうなるのかは、多くの保護者が気になるところでしょう。特に中学生は、高校受験で内申点が大きなウエイトを占めるため、慎重に考えたいポイントです。
まず、出席扱いとなった学習活動は、正式な「出席」として学校の記録に反映されます。これは、単なる欠席扱いにはならないため、結果として内申点を下げる直接的な原因にはなりません。つまり、家庭学習やフリースクールでの学びがきちんと評価対象になるということです。
そのうえで重要なのは、内申点は単に「出席日数」だけで決まるものではない点です。授業への参加態度や提出物、試験の結果など、総合的な評価によって決まります。つまり、出席扱いになったとしても、学習の質や取り組み姿勢が評価されなければ内申点アップにはつながらないのです。
例えば、オンラインフリースクールや自宅学習でも、レポート提出やテスト、面談を通じて学習成果を確認し、それがしっかり評価される仕組みが整っていれば、内申点に反映される可能性は十分にあります。逆に言えば、形式的に出席扱いとなっても、学習の中身が伴わなければ期待するような評価は得られないでしょう。
また、学校側がその学習活動をどのように評価するかは、事前に確認しておくことが大切です。必要な書類の提出や、定期的な進捗報告を求められるケースもあるため、学校との連携をしっかり取ることが内申点対策としては欠かせません。
このように考えると、出席扱い制度は「内申点の土台を守る仕組み」であり、最終的な評価を高めるためには、子どもの日々の努力と学校との密な連携が必要不可欠だと言えるでしょう。
オンライン授業の出席扱い制度について、詳しくは文部科学省の公式資料をご確認ください。最新の制度や基準についての情報は、以下から確認できます。▶ 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方」