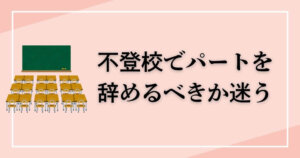私たちは「お金」を学ばずに大人になった
「税金って、どこにどう使われてるの?」「年金って本当に返ってくるの?」こんな素朴な疑問を、誰かにちゃんと教えてもらった記憶がない。そう思ったことはありませんか?
大人になって仕事をし、給料をもらい、家族を支えながら暮らしていく中で、ようやく世の中の「お金の仕組み」の存在に気づき始める私たち。けれど、それはあまりに遅すぎるようにも思えるのです。

なぜ「税金」や「お金」を学ばずに大人になったのか?
学校は「税」も「政治」も教えない
国語、算数、理科、社会、英語。
一見、バランスの取れた教育内容に見えるかもしれませんが、実際には「暮らしに密接する知識」、特にお金に関する知識はほとんど扱われてきませんでした。
「税金の使い道」や「年金制度の仕組み」、「保険の選び方」などは、教科書に載っていてもごくわずか数行。しかもそれらは、“テストに出ない”からと軽く流されてしまうことがほとんどです。
GHQが塗りつぶした「問い」の教育
戦後、日本の教育制度はGHQによって大きく作り変えられました。そこには明確な意図がありました。
GHQは、軍国主義的思想を排除し、民主主義を根付かせるために教育内容を全面的に見直しました。しかしその一方で、「政治」「経済」「国の仕組み」に関する内容については、意図的に“距離を置かせる”方向に再編されていったのです。
黒塗りにされた教科書。削除された歴史的文脈。
結果として私たちは、国家と個人、税と生活の関係性を“考えさせられないように洗脳された”のでしょう。
「お金のことは知らなくていい」という呪い
「お金の話は下品だ」「子どもにはまだ早い」
日本では長らく、こうした価値観が根付いてきました。その裏には、“お金の知識を持たない方が管理しやすい”という国の構造も見え隠れします。
本来は生活に必要な知識であるはずの「金融リテラシー」が、“大人の話”として遠ざけられ続けてきた結果、私たちは社会に出てから戸惑うことになります。
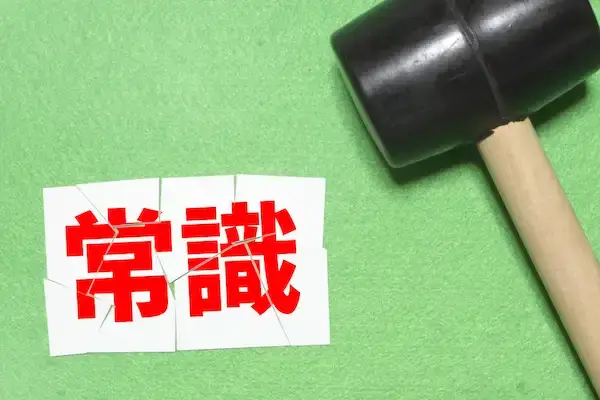
あなたは誰のために働いていますか?
給料明細を見ればわかる「社会のルール」
会社からもらった給料明細を開いてみると、まず目に飛び込んでくるのは、数々の「控除」欄。
- 所得税
- 住民税
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 雇用保険料
額面から差し引かれた後の「手取り」は、思ったよりも少ない。
「えっ、こんなに引かれてるの?」と驚いた人も多いはず。
実質の負担率は50%超
実際、日本人の平均的な生活者の税・社会保険負担率は、
- 所得税+住民税:約15%
- 社会保険料:約15%
- 消費税+その他間接税:約10〜15%
合計すると、手取りの半分近くが国や自治体に回っていることになります。
つまり、見方を変えると…家族のためと思って働いていた1年間のうち、1月から6月までの半年間は「自分と家族のため」ではなく、「国のために働いている」という計算です。
それを誰も教えてくれなかっただけ。

子どもに伝えたいのは「計算式」ではなく「構造」
なぜ税金の話を“家庭の会話”にしてこなかったのか?
「子どもにはまだ難しい」そう思って、お金や税金の話題を避けてきた家庭も多いかもしれません。
でも、子どもは意外とよく見ています。「なんでお父さんは朝早くから帰りが遅いの?」 「どうして欲しいものが買えないの?」
そんな疑問にこそ、税やお金の話を“生活に根付いたもの”として伝えるチャンスがあるのではないでしょうか。
「働く意味」を伝えるために必要な“問い”
「なぜ働くのか?」「そのお金はどこに消えるのか?」
それは、ただの計算問題ではなく、人生そのものの構造です。
- どうすれば家族の幸せにつながるのか?
- どうすれば不安を減らせるのか?
これが正解という答えのない問いを一緒に考えることが、「これからの教育」に必要なのだと思います。

日本人の金融教育はこれからどう変わるべきか?
「貯金だけ」から抜け出せない日本人
長年、「貯金は美徳」とされてきた日本。
でも、今の時代、それだけでは家計は守れません。物価は上がり、円の価値は相対的に下がり、年金制度も先行き不透明。
「お金の増やし方」「守り方」「使い方」まで含めた金融教育が、今こそ必要とされています。
世界では義務教育で“投資”も教えている
スウェーデンやアメリカ、オーストラリアなどでは、10歳前後から金融教育が始まります。
- 株とは何か?
- 税金とは誰のためにあるのか?
- 住宅ローンをどう選ぶのか?
そんな話を“当たり前”に学ぶからこそ、社会参加の意識も高まり、投票率や納税意識にもつながっていくのではないでしょうか。
「知ること」は、守ることでもある
お金のことを知らないまま大人になった私たち。でも、これからの子どもたちには、同じ思いをしてほしくない。そう感じている親世代も多いはずです。
税金のこと、社会保障のこと、経済のこと。難しくてもいい。わからなくてもいい。
大切なのは「知ろうとすること」「問い続けること」。自分の人生を、他人任せにしないために。
“知らされてこなかった”ことを、今こそ私たちが“知り直す”ときなのかもしれません。

私たちへの問い
知識よりも「思考力」が求められる時代へ
今、あらゆる知識はAIやインターネットが瞬時に答えてくれる時代です。
年金の制度や税制の仕組みを正確に覚えるよりも、「なぜこうなっているのか?」「誰にとって得なのか?」と問い続ける力が、これからの時代に求められます。
AIは暗記の達人です。だからこそ、私たち人間は、“意味を問う力”や“視点を切り替える力”を育てる必要があるのです。
金融教育を“暮らしの会話”から始める
「為替が円高だとどうなるの?」「インフレってなんで起きるの?」
こうしたテーマも、日常の暮らしに紐づければ、意外と子どもにも伝わります。
- 為替が円高になると、輸入品が安くなる=食卓の物価が変わる
- 投資信託は「未来の自分にお金を預けている」という考え方
難しい理論ではなく、“暮らしの実感”として伝えることが、金融教育の第一歩です。
子どもと一緒に「世界経済を自分ごと化」する
「今日ニュースで見たアメリカの話が、うちの電気代に関係してるんだよ」
そんな風に、世界経済が“遠いこと”ではなく、“自分たちの暮らし”とつながっていると体感できると、子どもは面白がります。地球の裏側の戦争が、うちの冷蔵庫の中身に影響してくる─
そういう視点を持つことは、未来を生きるための「力」になるのではないでしょうか。

未来の子どもに必要なのは“自分で考え抜く力”
「みんながそうしてるから」「テレビで言ってたから」 それだけを判断基準にするのではなく、
- 本当にそれでいいの?
- 他に選択肢はないの?
- 自分はどうしたいの?
そうした問いを持つことで、人生の舵を他人に任せず、自分で握る力が育っていきます。
AI時代の中で“人間として残る力”とは何か?
AIはすでに、医療診断、法律相談、株式予測までこなせる時代です。けれど、AIは「問い」を生み出すことや、「共感」「直感」「葛藤」を理解することができません。
だからこそ、人間に残された力とは──
- 自分で考える力
- 他人の痛みに想像力を持てる力
- 不確実な中で選択をする力
それこそが、AI時代において人間であることの証明になるのではないでしょうか。たとえ全部は教えられなくても、「一緒に考えよう」と言える親でありたい。
それだけでも、子どもの学びは変わっていくと私は信じています。
関連リンク☟
📘 金融庁|中学生・高校生のためのお金の知識👈高校生のための金融リテラシー講座
OECD|世界の金融教育に関するガイドライン 👉OECD/INFE 金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則